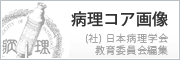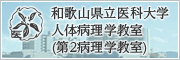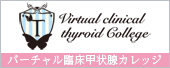細胞診専門医、細胞検査士の方へ
神戸常磐大学細胞検査士養成コース4期生
2014/12/23
2014年に神戸常磐大学を退職し、細胞検査士養成コースのことは気がかりだったのですが、とうとう集中講義1日だけの応援となりました。少し心配していたのですが、うれしい知らせが届きましたので、ご報告いたします。
本年卒業の4期生15名は、1次試験合格13名(86.6%)、2次試験合格12名(92.3%)1次、2次合わせて、15名中12名80%と今までの中で最高の合格率を獲得しました。4期生は私と一緒に神戸常磐大学に入学し、1年では私が学年担任であり、解剖学、病理学、組織学実習など多数の教科を担当した思いで深い学年です。高い合格率を得られたのは、各人のたゆまぬ努力と存じます。努力が報われることを体験できた君たちが、これから多くの困難に直面した時、この成功体験を生かし、乗り越える努力ができる人に変身できたと期待しています。12名の未来に幸多きことを願っています。
また応援いただいた外部非常勤講師の皆様の献身的なご援助の賜物と、細胞検査士養成コースの責任者であった者として、退職した身ではありますが、心より深く御礼申し上げます。
さらに嬉しかったことは、今まで合格できていなかった既年度卒業生4名も合格し、私が在職3年間で卒業研究ゼミを担当した12名全員が合格したことです。おめでとうございます。つらい思いもあったと思いますが、すべての苦労が楽しい思い出、笑いの種にできるようになったのは、覚道ゼミ卒業生12名にとって大きな自信になることと信じています。おめでとうございます。
category: 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 近況報告 comment: (0)
甲状腺外科学会2014福岡(山下会長)
2014/12/23
第47回日本甲状腺外科学会、2014年10月30日福岡で、ランチョン講演『甲状腺細胞診』を担当しました。甲状腺細胞診は、すでに確立された技術、術前診断法の要であります。しかしまだ臨床医に知っていただきたいことは、病理医の立場から、たくさんあります。甲状腺腫瘍の治療では鑑別困難が問題であり、鑑別困難という診断用語から、臨床医だけでなく細胞診を担当する病理医の中にも、細胞診では判らないので(ゴミ箱のように)鑑別困難に入れるのだと誤解している方が多くあります。良性か悪性かの判定はできないのですが、良性でもない、悪性でもない中間(癌の前駆病変,境界病変)の病変が多く含まれていることが判ってきました。今までこれを転移、浸潤のある出来上がった癌と、臨床医の皆様は混同していたのです。まだ癌かどうかわからない初期の癌、癌になる前の前駆病変、癌と紛らわしい良性病変、予後のいい非浸潤癌などが、鑑別困難に診断される多くの病変です(これ以外に標本不良のため診断が困難なものがあります)。これは、他の領域たとえば婦人科子宮頚部細胞診では、良性と扁平上皮癌の間に、前癌病変である異形成(Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion, High Grade Intraepithelial Lesion)、初期浸潤癌などが設定され、これらの病変は細胞診では、扁平上皮の異型の程度から、HSIL, LSIL, ASCH, ASCUSなどと詳細に診断されます。しかし甲状腺細胞診では、組織診断での前駆病変診断基準が未確立のため、細胞診鑑別困難の診断と対応する甲状腺癌の前駆病変、初期癌の対応は詳しく分析されていません。子宮頚部の扁平上皮病変のようにはまだうまくいかないのですが、これから細胞診鑑別困難の亜分類が面白くなると思っています。日本甲状腺学会は、これを世界に先駆けて取り入れました。これは伊藤病院の外科医鳥屋先生が始められた鑑別困難の亜分類です。また隈病院の宮内先生が実践された方法に準じています。この分野の先輩である宮内先生に座長を担当いただいたことから緊張している様子が写真からお分かりいただけると思います。また会長招宴では高見先生、加藤先生と歓談することができました。山下会長色々とご配慮ありがとうございます。
category: 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 臨床医の方へ comment: (0)
Jiangsu Institute of Nuclear Medicine
2014/10/21

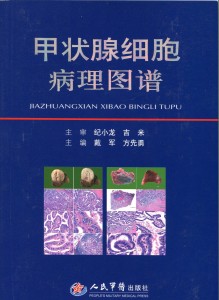
 I have an opportunity to visit at the Jiangsu Institute of Nuclear Medicine, to create a new friendship communication with Prof Daijun, Prof Jimmy and other members. They recently published a new textbook of thyroid cytology, ”甲状腺細胞病理図譜、人民軍医出版社、ISBN 978-7-5091-6180-7”, the first textbook of thyroid cytology written in Chinese language. Its remarkable point is that most of their illustrations are from HE stained conventional smear samples, significantly different from Papanicoloau stain. These are good illustrations and have a good correlation to HE features in histology. I found that dry artifacts did not create any problems in samples stained with HE in comparison to those often create serious staining problems in Papanicoloau samples. They have a good teamwork for patients with thyroid diseases and composed of pathologists, endocrinologists, surgeons and radiologists. I found they have more than 1500 thyroid surgerys including more than 700 cancer cases per year.
I have an opportunity to visit at the Jiangsu Institute of Nuclear Medicine, to create a new friendship communication with Prof Daijun, Prof Jimmy and other members. They recently published a new textbook of thyroid cytology, ”甲状腺細胞病理図譜、人民軍医出版社、ISBN 978-7-5091-6180-7”, the first textbook of thyroid cytology written in Chinese language. Its remarkable point is that most of their illustrations are from HE stained conventional smear samples, significantly different from Papanicoloau stain. These are good illustrations and have a good correlation to HE features in histology. I found that dry artifacts did not create any problems in samples stained with HE in comparison to those often create serious staining problems in Papanicoloau samples. They have a good teamwork for patients with thyroid diseases and composed of pathologists, endocrinologists, surgeons and radiologists. I found they have more than 1500 thyroid surgerys including more than 700 cancer cases per year.
category: 同門会 , 病理医の方へ , 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 臨床医の方へ , 近況報告 comment: (0)
第5回奈良甲状腺研究会
2014/09/21
9月20日、第5回奈良甲状腺研究会が、奈良県立医科大学の厳橿会館で開かれました。参加したのは2回目で、今回より顧問としておよびいただき、甲状腺細胞診について20分の講演時間を頂きました。今甲状腺細胞診は大きく変化し、分子診断が取り入れられるなど変革の時代を迎えています。甲状腺細胞診の概念を変えて、臨床での役割を向上させたいと考え、喜んでお引き受けいたしました。
この後、10月30日福岡の第47回甲状腺外科学会でもランチョンとして、細胞診で講演させていただく予定です。また、来春の4月25日日本内分泌学会での教育講演でも、甲状腺細胞診を予定しています。現状の一般の細胞診では、半数程度以上が結論の出ない診断(検体不適+鑑別困難+悪性疑い)が帰ってくるなど、臨床医の信頼の得られない、役に立たない甲状腺細胞診となっています。これを変えていきたい。目標は、(結論の出ない診断を20%以下に抑え)信頼される、頼られる細胞診に変えたいと思っています。興味のある方は是非ご参加ください。
なお、この第5回奈良甲状腺研究会には、昔の同僚である和歌山県立医科大学赤水教授も特別講演で参加され、和歌山のことを懐かしく思い出しました。甲状腺学会理事長として活躍されており、来年の国際甲状腺学会シンポジウムに演者として推薦したと伺いました。私の仕事が広がることに感謝しています。
category: 病理医の方へ , 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 臨床医の方へ comment: (0)
バーチャル臨床甲状腺カレッジ
2014/09/06
日本甲状腺学会はバーチャル臨床甲状腺カレッジを設定し、専門医をめざす修練医、甲状腺疾患を学ぶ人々に教材として提供しています。私も基礎解剖学と、IgG4甲状腺炎を担当しています。2014年9月内容が更新されました。以下のアドレスよりご覧いただけます。お時間のある時に試してください。
URL: http://www.thyroid-college.jp/
category: 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 臨床医の方へ comment: (0)