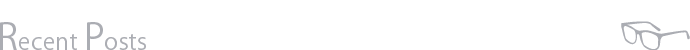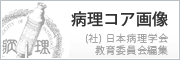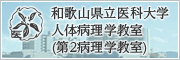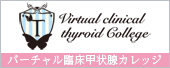竹腰先生と稲田先生の教授昇任お祝の会
2015/05/05
竹腰先生(東海大学医学部生体防御学)、稲田先生(藤田保健衛生大学坂文種病院病理診断科)の教授昇任お祝いの会が、第104回日本病理学会総会開催時、2015年4月30日名古屋国際ホテルで開かれました。また病理の皆がお世話になった研究推進部の伊東丈夫先生が定年退職されることになりました。これらを祝い、久しぶりに東海大学病理学教室の同門会の懐かしい顔が集まりました。東海大学病理学教室は細胞生物学中根教授、第1病理学玉置教授、第2病理学渡辺教授が大講座、研究グループを運営されました。この中から、東海大学医学部病理学教室開設後40年の間に22名の教授が誕生したことは特筆すべきことと存じます。名伯楽渡辺慶一先生、玉置憲一先生、中根一穂先生に感謝しています。
東海大学内部昇格:垣生園子(免疫学)、長村義之、上山義人、多田伸彦(健康科学部)、佐藤慎吉(大磯分院)、中村直哉、中村雅登(再生医療科学)、竹腰進(生体防御学) 他大学で教授に採用された者:守内哲也(北海道大学)、鬼島宏(弘前大学)、名倉宏(東北大学)、安田政実(埼玉医科大学)、秦順一(慶応大学)、増田しのぶ(日本大学)、森一郎(国際医療福祉大学)、山崎等(北里大学)、堤寛(藤田保健)、稲田健一(藤田保健)、覚道健一(和歌山医大)、鴨志田慎吾(神戸大学保健学科)、玉内秀一(愛媛県立医療技術大学 )、小路武彦(長崎大学解剖学)甲状腺癌被包型乳頭癌濾胞亜型が変わりました。
2015/04/16
2015年3月20日、21日米国ボストンにて、写真の病理医24名、臨床医3名、患者代表1名が集まり、現在癌とされている甲状腺腫瘍(被包型乳頭癌濾胞亜型の浸潤転移のないもの)の呼称を変更する会議がもたれました。この腫瘍は米国で癌として治療され、相当数の患者が、甲状腺全摘出、放射性ヨード治療を受けていました。しかし、24名の病理医で再検証した109例の症例(14年経過観察、放射性ヨード治療をされなかった症例)の予後から、再発転移が起こらないことが確認され、この確認を受け、NIFT (non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features)と呼称を変更することが決定されました。癌が良性の前癌的病変に変更される歴史的場面に立ち会えたことを喜んでいます。これから多くの患者の治療にインパクトがあることを期待します。患者が診断名に意見を述べたり、臨床医が注文を付けたりするのは、日本ではない光景でした。
甲状腺癌の過剰診断、過剰診療、過剰治療について。
2015/02/09
現在米国では(文献1,2参照)、甲状腺癌だけでなく、乳癌、前立腺癌などで、検診による早期発見、早期治療の功罪が問題とされています。早期発見早期治療により救われた生命よりも、治療の必要のない病変(治療しなくても生命予後に悪影響のない病変、近藤誠先生の『がんもどき』など)を、多数発見し、『がん』として治療することにより、
A) 癌死亡の減少に貢献していない。(癌患者は増えたが、癌死亡数は増えていない)
B) 医療費の無駄遣いをしている。
C) 患者を苦しめている。(治療しないで放置しても無害な病変を、お節介にも見つけて、無駄で有害な治療をしている)
などと議論されています。患者の皆様、臨床医の皆様どのようにお考えでしょうか?
患者の立場としては、見つかった病変を治療しないで持ち続けることは、たぶん不安でたまらないでしょう。少数かもしれませんが、本当の癌(治療しないで放置すると進行し、癌のために死亡する)かもしれません。後で後悔することがないように、普通の人は、迷うかもしれませんが、多くの場合、治療を受けようと考えるのではないでしょうか?このホームページの『医療の不確実性』の項を参照ください。
ここでは2点に分けて議論しなければいけないと考えています。
1. 病変の性質を正確に判断し、治療したほうがいいか、治療しないでそのまま持ち続けるかの判断をする。
ここで病理医の役割(本当の癌か癌に類似した無害な病変の区別)があります。
2. 治療が必要と判断した時、治療方法の中から、最も適した(治療効果が高く、治療による不愉快な、悪影響を最小にする)選択肢は何かを考える。
治療の中心を担うのは臨床医ですが、ここでも病理医の示す、病変の性質、病気の進み具合(病期)の診断が、治療方法の選択に重要な参考資料、判断根拠となります。
1. Esserman LJ et al: Addressing overdiagnosis and overtreatment in cancer: a prescription for change. Lancet Oncol, 15:e234-242, 2014.
2. Luster M et al: Differentiated thyroid cancer-personalized therapies to prevent overtreatment. Nat Rev Endocrinol 10:563-574, 2014.
A) 癌死亡の減少に貢献していない。(癌患者は増えたが、癌死亡数は増えていない)
B) 医療費の無駄遣いをしている。
C) 患者を苦しめている。(治療しないで放置しても無害な病変を、お節介にも見つけて、無駄で有害な治療をしている)
などと議論されています。患者の皆様、臨床医の皆様どのようにお考えでしょうか?
患者の立場としては、見つかった病変を治療しないで持ち続けることは、たぶん不安でたまらないでしょう。少数かもしれませんが、本当の癌(治療しないで放置すると進行し、癌のために死亡する)かもしれません。後で後悔することがないように、普通の人は、迷うかもしれませんが、多くの場合、治療を受けようと考えるのではないでしょうか?このホームページの『医療の不確実性』の項を参照ください。
ここでは2点に分けて議論しなければいけないと考えています。
1. 病変の性質を正確に判断し、治療したほうがいいか、治療しないでそのまま持ち続けるかの判断をする。
ここで病理医の役割(本当の癌か癌に類似した無害な病変の区別)があります。
2. 治療が必要と判断した時、治療方法の中から、最も適した(治療効果が高く、治療による不愉快な、悪影響を最小にする)選択肢は何かを考える。
治療の中心を担うのは臨床医ですが、ここでも病理医の示す、病変の性質、病気の進み具合(病期)の診断が、治療方法の選択に重要な参考資料、判断根拠となります。
1. Esserman LJ et al: Addressing overdiagnosis and overtreatment in cancer: a prescription for change. Lancet Oncol, 15:e234-242, 2014.
2. Luster M et al: Differentiated thyroid cancer-personalized therapies to prevent overtreatment. Nat Rev Endocrinol 10:563-574, 2014.