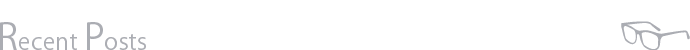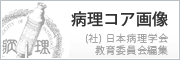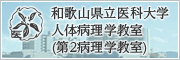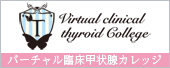第15回国際甲状腺学会、米国オーランド市
2015/11/13
10月18日から23日にフロリダ州オーランドで国際甲状腺学会が開催されました。眼科のガリティー教授(メーヨ医科大学)、膠原病内科のKhosroshahi教授(エモリー大学、名前の発音が分かりません)とともにIgG4関連疾患のシンポジウムを担当しました。李先生、隈病院西原先生、和歌山医大竹島先生、山下クリニック猪俣さんたちとの共同研究で進めてきた、『IgG4甲状腺炎』について、このIgG4甲状腺炎の疾患概念を確立するために、私にとっては、和歌山医大での仕事を、この国際学会で、まとめとすることができました。このIgG4甲状腺炎の疾患概念を、欧米で受け入れてもらえず苦労した原因はたぶん(原因は分かりませんが)IgG4甲状腺炎、IgG4関連疾患が、日本人に多い病気、欧米ではたいへん少ない病気であることが、原因ではないかと思っています。本学会では日本から多くの参加者、発表があり、地理的、人種的違いによる疾患の違いや、社会的背景、宗教観、論理的思考の違いなどからくる治療方針に違いがることなど、多くの意見交換がなされました。日本からは隈病院の甲状腺微小乳頭癌のシンポジウム、宮内昭先生のAOTA受賞講演、鈴木教授の福島原発事故後の甲状腺検診報告、など、一時代を画する国際甲状腺学会でした。
和歌山県立医科大学創立70周年記念式典
2015/11/01
第48回甲状腺外科学会学術集会(東京)
2015/10/31
第48回甲状腺外科学会学術集会が伊藤病院伊藤公一会長のもと開催されました。病理が関与する内容として、癌取扱い規約の改定が公表されました。ここではべセスダシステムが甲状腺細胞診に採用されると発表されました。加藤、廣川、亀山先生たちと私の4名の病理医が尽力し、日本で独自に発達した甲状腺診断様式を、The Japanese System(日本方式)として命名し、日本甲状腺学会より発表したのですが、残念なことに、これは採用されず、これと異なるべセスダ診断様式(アメリカ様式)を、癌取扱い規約に採用すると公表しました。The Japanese Systemは、写真の伊藤病院の鳥屋先生が尽力された伊藤病院で発達した診断方式です。伊藤公一会長の主宰されたこの学会で伊藤病院の診療の伝統を否定する内容が公表されたのは、何という矛盾なのでしょうか。日本独自の文化、哲学、診療方針を大切にしてほしいと思いました。しかし公表された内容を見ると、
1)嚢胞は、検体不適として再検査するべセスダ様式は採用しない。2)診断名は直訳は分かりにくいので短縮形を用いる。3)濾胞性腫瘍の診断基準を変更する。4)悪性の確率を示さない。5)臨床的対応を示さない。などべセスダ診断様式と呼ぶことができないほどの多数の重要な変更点を加えたものとなっています。1)2)3)については、どちらかというと日本甲状腺学会の診断様式(The Japanese System)に近いと思われます。また4)5)については、The Japanese Systemはべセスダに準拠し悪性の確率を推定し、臨床的対応にも言及しています。2つの診断様式を比較した時、べセスダに近いのはThe Japanese Systemの方かもしれないと思いました。The Japanese Systemは、べセスダとの互換性を意識し、違いを強調し発表いたしました。癌取扱い規約ではべセスダを意識し、名前をべセスダにしたのですが、結果的には似て非なるものかもしれません。
category: 病理医の方へ , 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 臨床医の方へ comment: (0)